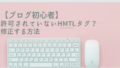今年のお盆もお墓参りはしませんでした。
お墓が地方にあるのと、子どもが小さいので人混みは避けたかったことが理由。
朝晩ひんやりして初秋の風を感じながら、お彼岸はいけるといいなと願ってみました。
今日は名残惜しいお盆のお話です。
亡くなった人も名残惜しい?
お盆は、ご先祖様の例があの世からこの世に戻ってくる日。
でも、この世に居られる期間を決めておかないと、いつまでたってもあの世に帰れず、この世にとどまってしまうため、期間を決めているのだそう。
お迎えとお見送り
お盆の始まりには霊を迎える「精霊迎え」、終わりには霊を見送る「精霊送り」をします。
迎え火や送り火もその一つですね。
ちなみに、迎え火と似たようなものに盆提灯(ちょうちん)があります。
霊をお迎えするための目印であり、また先祖の霊が滞在していることをお知らせするものとされています。
私の地域では、初盆に盆提灯を玄関や軒先に飾ることが慣例となっています。
あの世の方へのおもてなし
お盆には様々な行事を行ますよね。
花火や盆踊りなどお盆に行うお祭りは、ご先祖様の霊がこの世に未練を残さないように、この世の人があの世の人に向けた気遣い。
要するに、おもてなしです。
中でも、お寺の境内や広場で行う「盆踊り」は、お盆最大のイベントです。
盆踊りにも種類があって、やぐらの上でたたく太鼓を中心に、人々が輪になって踊り続ける姿を「輪(わ)踊り」といい、富山県富山市八尾町の「おわら風の盆」のように人々が列になって街中を踊り歩く盆踊りもあります。
盆踊りのルーツは「踊り念仏」
盆踊りのルーツは念仏を唱えながら練り歩く「踊り念仏」にあるのだそうです。
踊り念仏は、もともとは自分で念仏を唱えながら踊っていたの「念仏踊り」が、踊る人と念仏を唱える人に分かれた「踊り念仏」となったのだそう。
徳島県の代表的な踊り、「踊る阿呆に見る阿呆、同じ阿呆なら踊らにゃ損々」の、阿波踊りも「踊り念仏」と言われています。
国内最大級の阿波踊りは、お盆最大のイベント。
さぞかし、ご先祖様もにぎやかにお過ごしでしょう。
私の育った地域では、盆踊りの前に小さな花火大会が開催されていました。
迎え火もかねていたのかなぁ。
花火を見たり、踊ったり、あの世からいらしたご先祖様へおもてなしするこの世の人も、おもてなしを受けるご先祖様も、この世に帰ってきたら、きっと楽しんでくれているのでしょうね。
穏やかな秋でありますように
こんなに楽しくなったら、かえってあの世に帰れなくなっちゃうんじゃないの?と思ったりして。
おもてなす方も、おもてなしを受ける方もお別れが名残惜しくなりますね。
もうすぐ、富山県の「おわら風の盆」。
立春から数えて210日目に行う理由は、ご先祖様への慰めの他に、台風を沈め、五穀豊穣を願う意味もあるのだそうです。
3日3晩踊り続ける踊り手さんの姿は、テレビ越しでも十分優雅さが伝わってきます。
どうか穏やかな秋でありますように。
人との接触を避けて生活することが当たり前になった今、どこにいても、自然やご先祖様を敬う気持ちは忘れずにいたいものです。