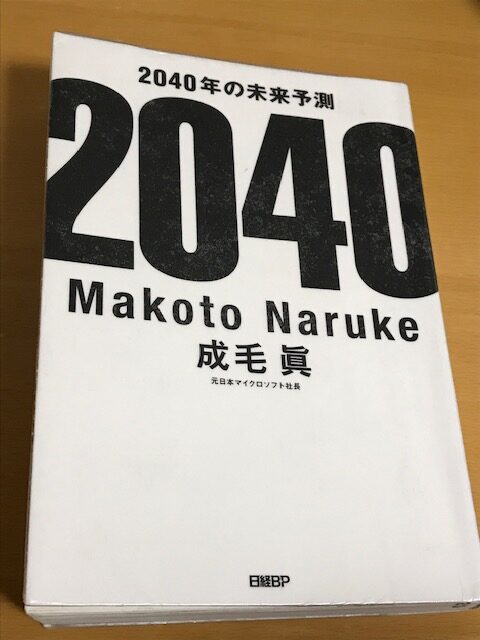天気予報の精度はとっても高いですよね。
20年くらい前の天気予報では、予報士さんが「気象衛星ひまわりからの映像です」と話していたっけ。
衛生が地球の周りを回っていて、雲の動きを地上にいる私たちに教えてくれるって単純だけど、すごいこと。
洗濯物を干したり取り込んだり、生活に密着した天気予報は毎朝のチェックに欠かせない情報です。
それと、歳時記。
昔の人の言い伝えは侮れません。
二十四節気だと、今は「雨水」。
降る雪が雨に変わって、積もった雪や張っていた氷が解けて水になっていく意味。
私が住んでいる街はそこまで厳しい寒さではないけれど、晴れれば日差しも明るくなり、雨模様では雨音に力強さがこもっているようで春の気配が感じられます。
未来予想図
今回読んだ本は元日本マイクロソフト株式会社社長の成毛眞さんの『2040年の未来予測』(2021/1/21)日経BPです。
表紙に太くて大きく2040と書いてある大変インパクトのある本。
昨年読んだ『2030年すべてが「加速」する世界に備えよ』 ピーター・ディアマンディス (著), スティーブン・コトラー (著), 土方奈美 (翻訳) NewsPicksパブリッシング (2020/12/24)を思い起こしてしまい思わず手に取ってしまいました。

この本は、日本を俯瞰して今後どうなっていくのか、現実と照らし合わせて未来予想図を展開してくれる本です。
安宅和人さんの『シンニホン』と比べるとだいぶ悲観的にも思えましたが、でも、多分そうかもなぁと思うことの方が多かったのも事実。
自分が新聞やニュース、インターネットで集めた情報が整理されて本になった感じで割とスイスイ読めました。
未来なんて見据えず、今を必死に生きることは素晴らしいことだけど、新しい変化に少しでも対応するために、来るべきものは何か、あらかじめ予測を立てておくこと、知識は蓄えておくことが重要なんだなと思わせてくれました。
想像しえないことも起こるかもしれない怖さ
著者は、テクノロジー、経済、生活、天災と分野ごとに未来予測をされています。
テクノロジーに関しては、私自身は乗っかっているのが精一杯で、今のスマートフォンですら使いこなせてないという現実。
kindleが便利なんだということは、分かっているのだけれど、どうしても紙の本を手に取ってしまうし、現状維持を望んでいる一人です。
この本を読み進めていくと、分野ごとの課題はあるけれど、それを一つにまとめると実はシンプルな問題なんだということが、ぼんやりと浮かんできます。
それは、自分が環境に慣れること。
人間の寿命は長い人でも120歳くらいですが、地球は生まれてからすでに46億年も経っています。
山に入ると、人間より長生きしている木が沢山あるし、虫だって、植物だって環境に合わせて進化をしてきています。
四季を感じられる日本では、すぐそばに自然の美しさを持っている反面、自然災害とも隣り合わせ。
いつ何が起きても、へこたれず環境に慣れることが、前を向いた人生になるんじゃないのかなと思いました。
影もあれば陽もある
日本の未来を予測した本を読むと、経済は良くて横ばい、人口は少子高齢で高齢者ばかりの国。
給料は上がらず、社会保険料ばかりが上がるという、なんだか桃太郎電鉄のビンボーが付いているような話が一般的です。
多くの人が予測しているように、多分そうなるのかもしれない。
でも、誰にでも伸びしろはあるし、日本という国の伸びしろだってあるんじゃないの?
すごく楽観的だけど、そう思ってしまうのは、私がまだ相対的に若い部類に入るからでしょうか。
人間よりも得意な分野はAIをはじめとするテクノロジーに任せていくんでしょう。
そして、人間の生活も変化をしていく。
なんだか想像がつかなくて怖いけど、30年前と比べたらスマートフォンだって無かったわけだし、電子マネーだって「なんだ?それ?」だったわけじゃない。
意外と生活の中にテクノロジーが入り込んでも、上手いこと取り込んで便利に生活をしているのかもしれないな。
楽天的かもしれませんが、自分では何ともできない大きな波が来ているような感じがして、なるようになるしからんわいっ!といったところ。
自分ができること
地震が来るかもしれないし、火山が起こるかもしれない。
エルニーニョ現象はもうすぐ終わるみたいですが、こういう地球規模の環境変化は、過酷だけど自分自身で対応するしかない。
経済だって生活だって、悲観しても先に進まない。
「どうして、こうなっちゃったの?」って思うこともあるけれど、過去を問い詰めても意味はないですよね。
だから、「どうしたら、いいかな?」と自分に問うてみることにしました。
地球が温暖化で大変なんだと聞いたら、「じゃ、買い物に行くときにエコバック持っていくわ」とか自分一人がやっても効果はないかもしれないけれど、そういう小さなことを辛くない範囲でやっていくことが、地球人としての使命なのかなとも思いました。
色々不満はあるかもしれないけれど、「どうしたら?」と考えていくと意外と問題はシンプルなのかもしれません。
この本で予測しているように、きっと近い将来、予測が現実になるんだと思います。
未来も現実も明るく過ごすのか、暗く過ごすのかはその人次第。
楽天的に考えて、環境に慣れる過ごし方を今、この瞬間から練習してみてもいいのかな。
この本を読んで少なくとも、私は前向きに生きてみようと思いました。