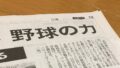先日、2019年に虐待を受けるなどして入院し、治療を受けた児童が帰れなくなっているというニュースを目にしました。
国の調査によると、治療の必要がなくなっても、帰り先や受け入れ先がないなどの理由で退院できずにいる子どもが、全国で327人にも上るそうです。
この人数が多いとみるか少ないとみるかは別として、子どもに居場所が無いって辛いことです。
退院できるのに、帰り先がなくて、やむなく入院していることに心を痛めました。
私にできることは、学んで調べることしかできないけれど、何かできないかな、なんて思いながら、どんなところが受け入れ先として考えられるのか、調べてみました。
生みの親のもとで生活できない子どもたち
日本では生みの親のもとで育つことができない子どもたちは約45000人に上るのだそうです。どこで暮らしているかというと、約80%が乳児院や児童養護施設などの施設で暮らしています。
生みの親以外で暮らす場合には以下のような施設があります。
「乳児院」
乳児院とは、さまざまな事情によって保護者との生活が困難な乳児を保護し、養育する施設のことを言います。
国、地方自治体、社会福祉法人が運営しています。
1歳未満の子どもたちが入所する児童福祉施設ですが、必要に応じて就学前まで入所することができます。
24時間乳児院で過ごすことになるので、子どもたちにとっては、家庭に変わる日常生活の場になります。
乳児院で過ごした子どもたちは大きくなると、親元へ戻ったり、里親に引き取られたり、児童養護施設へ入所したりするそうです。
「児童養護施設」
保護者のいない児童や虐待されている児童など、保護を必要とする児童を入所させ養育する児童福祉施設。
児童養護施設で生活できるのは、乳児を除く原則18歳まで(大学進学など必要に応じて22歳の年度末まで)です。
高校を卒業すると退所しなくてはなりません。
退所した人に行う相談や自立のための支援も行っています。
保護を必要とする子どもが家庭で暮らす方法
保護を必要とする子どもが、安心して家庭で生活する制度には、「養子縁組」と「里親制度」があります。
「養子縁組」
養子縁組は民法に基づいて法的な親子関係を成立させる制度です。
親権者は養親です。
養子縁組が成立した家庭には、金銭的な支援はない。
養子縁組には、普通養子縁組と特別養子縁組の2種類あります。
- 跡取りなど成人にも広く使われる制度。
- 年齢制限はなし(養親より年上は認められない)
- 生みの親とも育ての親とも縁が続く。
- 養親との離縁は可能。
普通養子縁組は生みの親と育ての親の両方とも縁が続くことで、4人の親がいることになります。
育ての親との縁は離縁することができますが、相続とか扶養とか結構難しい問題も絡んできそうな感じです。
- 保護を必要としている子どもが、実子に近い安定した家庭を得るための制度。
- 年齢制限は原則として15歳未満
- 生みの親との縁は途絶える。
- 養親との離縁はできない。
特別養子縁組は、名実ともに親子となります。
離縁したいと思ってもできないことがデメリットでしょうか。
ただし、保護を受けている子どもが、安定的に暮らすことを考えれば、特別養子縁組は理想的な形なのかもしれません。
「里親制度」
「里親制度」は、育てられない親の代わりに一時的に家庭内で子どもを預かって養育する制度です。
愛情と正しい理解を持った家庭環境で養育を提供されます。
年齢制限は原則として18歳までです。
厚生労働省によると、2018年現在、里親登録世帯数は12315世帯。
委託児童は5556人だそうです。
- 里親と子どもに法的な親子関係はない。
- 親権者は実親。
- 里親には、里親手当てや養育費が自治体から支給される。
里親と子どもとの間に、親子関係はありませんが、里親さんには自治体から里親手当(月額約9万円)の支給もあるので、子どもにとっては、環境的にも経済的にも安定した生活ができるのではないかと思います。
子どもたちに安定的な環境
私は子どもを叱らない日がないので、毎日反省の日々です。
子どもたちに安定的な環境ってどんなでしょうね。
ご飯やおやつがきちんと食べられて、お風呂に入れて、ゆっくり眠れて、身だしなみも整えてみたいな感じなのかな。
我が家でも、急に甘えん坊になってしまったり、できるのにやって欲しいとせがんできたり、癇癪を起したりしますが、そういう喜怒哀楽を素直に出せることは逆に恵まれたことなのかもしれません。
今の私に、他の子どもたちへ何かをすることは余裕がなくてできないけれど、自分の子どもたちに笑顔のある暮らしを与えることが、私にとっての役割なのかな、と思っています。
暗いニュースがある中で、目をそむけたくなることもありますが、じっくり調べて自分に置き換えたり、見つめ直してみたりする、きっかけにして家族の在り方を考えていきたいと思っています。