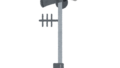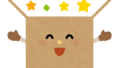我が家の末っ子に自我が芽生えてきました。
今までは、大きな声を出すこともなかったのですが、大きな声が出せると知ってからは、困ったことに所かまわずにギャーッと叫びます(笑)
電車やバスなどの公共交通機関などに乗車の時は、困ったもの。
昨年の今頃に読んだ本を思い起こしてみました。
読んだ本は、島村華子さんの『モンテッソーリ教育・レッジョ・エミリア教育を知り尽くした オックスフォード児童発達学博士が語る 自分でできる子に育つ ほめ方 叱り方』ディスカヴァー・トゥエンティワン (2020/4/17)
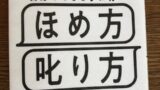
イラスト付きで、とても読みやすく、家事の合間でも1日で読める分量なのが嬉しい本です。
みつけた
我が家の末っ子は2歳になったばかり。
とにかく自分の興味がどんどん湧いてくるタイプの子ども。
自宅の中でも外でも、いろんなものに興味を示し触り舐めます😅
藪の中に入って、ササの葉で手や足に切り傷を作るのはいつものこと。
最近は私自身も学んで、多少暑くても薄手の長袖、長ズボンを履かせて怪我対策をしているところです。
道に落ちているものは、すべて遊びの道具。
落ち葉、木の枝、落ちているペットボトルから、空き缶、ゴミ…「あったよ!」と元気に持ってきてくれます。
ゴミはごみ入れに捨てたり、本人の気持ちを壊さないように対処しているつもりです。
自分で自分で
ここ数週間で自分でやりたがる気持ちも芽生えてきました。
お着替えも自分で。帽子をかぶるのも自分で。
着る服を選ぶことはまだしませんが、自分で何でもやりたがります。
最近興味を持っているのが、家事仕事。
私がお皿を洗おうとすれば、スポンジに泡をつけてほしいと、おねだり。
スポンジを渡すと、喜んで、泡をブクブクさせたり、お皿をフキフキする真似をします。
私が洗濯物を干そうとすると、「おてつだいします」とやってきて、小さな指で自分のハンカチをピンチに挟もうとします。
時間が無限にあれば、付き合ってあげたいものですが、時間は有限。
しかも家事は、短時間で済ませたい。
そういう思いから、一緒に家事をしたりしなかったりしているのが現実です。
せっかくやっていたのに
とにかく夢中になるのが得意な我が家の末っ子。
兄弟のバスで、楽しそうに遊んでいると、横取りされることもあります。
すると、「ギャーッ」力の限り怒り、泣き出します。
それだけでなく、抓ったり、叩いたりして抗議をしています。
ほぼ年子のケンカ。
ほぼ下の子が負けてしまい、泣かされてしまうのですが、時には上の子を叩いて、泣かしたりということもあります。
暴力はいけませんが、そのくらい気持ちの強い子。
自分が集中しているときに、邪魔されるのがとても苦痛なようです。
おかげで、バスや電車に乗ったときには、降りる駅なのに、「もっと、のりたい」と駄々を捏ねられるときも…
抱っこして、ギュっとしながらおろします。
自分の好きなことに集中することは良いことですが、集中しすぎることも考え物だなと思ったりします。
自分の気持ちは俯瞰する
モンテッソーリは、イタリア発祥で諸外国で取り入れられている教育法。
教育の基本的な考え方は「子どもには生来、自立・発達していこうとする力があり、その力が発揮されるためには発達に見合った環境が必要である」というもの。
モンテッソーリ教育は「日常生活」を大事にする考え方。
本を読んで感じたのは、まず子どもが何をしているのかを見守るということ。
親である自分の気持ちを横に置いて、子どもたちが何をしているのかを確認。
そのうえで、声を掛けるかどうかの判断をします。
子どもたちが夢中になっている遊んでいるときに、大人の都合で声を掛ければ、子どもたちは邪魔されたと感じるでしょう。
大人には、大人の事情があるけれど、子どもには子どもの事情があると認識する必要があるのです。
自分の気持ちは、自分の上にドローンでも飛ばすように、一旦俯瞰して見ること。
これが、子どもたちを見守る第一歩なんですね。
有限な時間、でも子どもたちに寄り添いたい、自分に課されている行動は、簡単なようなもので容易いことではないですが、気持ちを落ち着かせて穏やかに接していきたいなと改めて気づかされました。