子どもに対する欲というものは、常に出てしまうもの。
初めは笑ってくれただけで、嬉しかったのに。年齢が上がってくるにつれて、一人でやってみてほしいな。
頑張ってほしいなと背伸びもしてしまう。
個人個人の物差しで、見守ってあげる忍耐が必要なんですよね。
Eテレのできるかな
子どもたちと何となく見る番組『おかあさんといっしょ』
番組の中では、自分一人で食事をしたり、洋服を畳んだり、手を洗ったり、3歳くらいの子どもたちが、自分一人でやってみるコーナーがあります。
コーナーを見ながら、「テレビのおともだち。頑張って食べているね」とか「洋服畳めたね」と確認し合うのが、最近の流行り。
親である自分としては、このきっかけを、我が子自身にも当てはめて、行動に移らないかな~と欲張りな気持ちになるコーナーです。
今すぐでなくともいいことは、頭の中で分かっているのだけれど、年齢が近いとなると、「やっぱり、これはできた方がいいよね」とか「うちの子も…」という気持ちが芽生えてきてしまいます。
それが、思わず口をついてしまうのも事実。
人とは比べないと決めているはずが、何かのはずみに、親である私のタガが外れてしまうのです。
自立を考える
我が子が1歳くらいの時に出会った本。
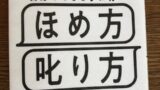
モンテッソーリという響きも初めてで、何のことやらわからなかった私に、思考の変化をもたらした本です。
モンテッソーリ教育の目的は、「自立していて、有能で、責任感と他人への思いやりがあり、生涯学びつづける姿勢を持った人間に育てる」こと。
概念というか、目的が達成されれば、素晴らしい一人の人間に育つはず。
そのためには、まず、自立を促さなければ。という考えに至ったわけです。
では、子どもにとって、自立とは何なのか。
食事が自分で食べられること?
お着替えが自分でできること?
トイレが自分で済ませられること?
大人である自分は、どうしても、行動の面をクローズアップしてしまいますが、精神的な自立のことを指すのではないかと思うのです。
つまり、自分の意見を表現できることではないかと思うのです。
自分の意見を表現できることは、子ども自身に自信が身についているということ。
自分が何でもやってみようという、不思議な力。
なんでもポジティブに考えられる力を支えることが、自分の役割なのかなとも思っているのです。
我慢比べ
子どもらしさを伸ばしてあげたい。
そして、自分に自信を持って欲しい。
このことを実現するには、私自身の忍耐が必要です。
それは、自分自身がマイナス思考に陥りがちになるから。
マイナス思考の大人が注目してしまうのは、できないことについて。
子どもが出来たことは、大人にとっては当たり前のこと。
だから、「できた」よりも、「できない」ことの方に注目してしまうのです。
自分に置き換えてみても、「できたね」と言われる方が、「どうしてできなかったの?」と言われるよりもはるかにやる気が湧き出てくるのは明確ですよね。
子どもは、まだ出来ないだけで、一人の人間。
そういう尊厳を認められれば、自分の支配下に置こうとしたりはしないはず。
寄り添うこと、伴走することが、一人の人としての成長を促し、子どもたちの自信につながり、自立へ向かわせるのでしょう。
自己投影
自分自身が良かれと思うことが、必ずしも良いこととは限りません。
自分に置き換えてみて、「こういう風に言われたら、嬉しいな」、「こういわれたら悲しいな」というちょっとした認識が意識を変えていくのだと思います。
それには、我慢や忍耐も必要。
そして多少面倒くさい。
でも、ゆくゆくは一人の人として、歩いていかなくてはならない子どもたちにとっては、環境って、たぶん一番大事。
子どもたちを成長させるのではなくて、自分も一緒に成長していくという気持ちを強く持って、日々の生活を送っていきたいものです。



